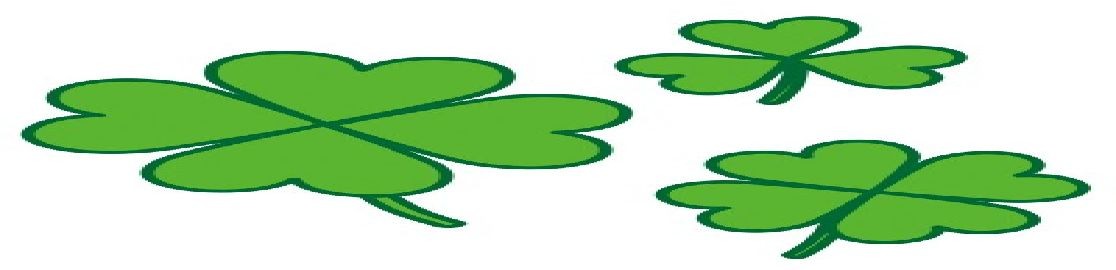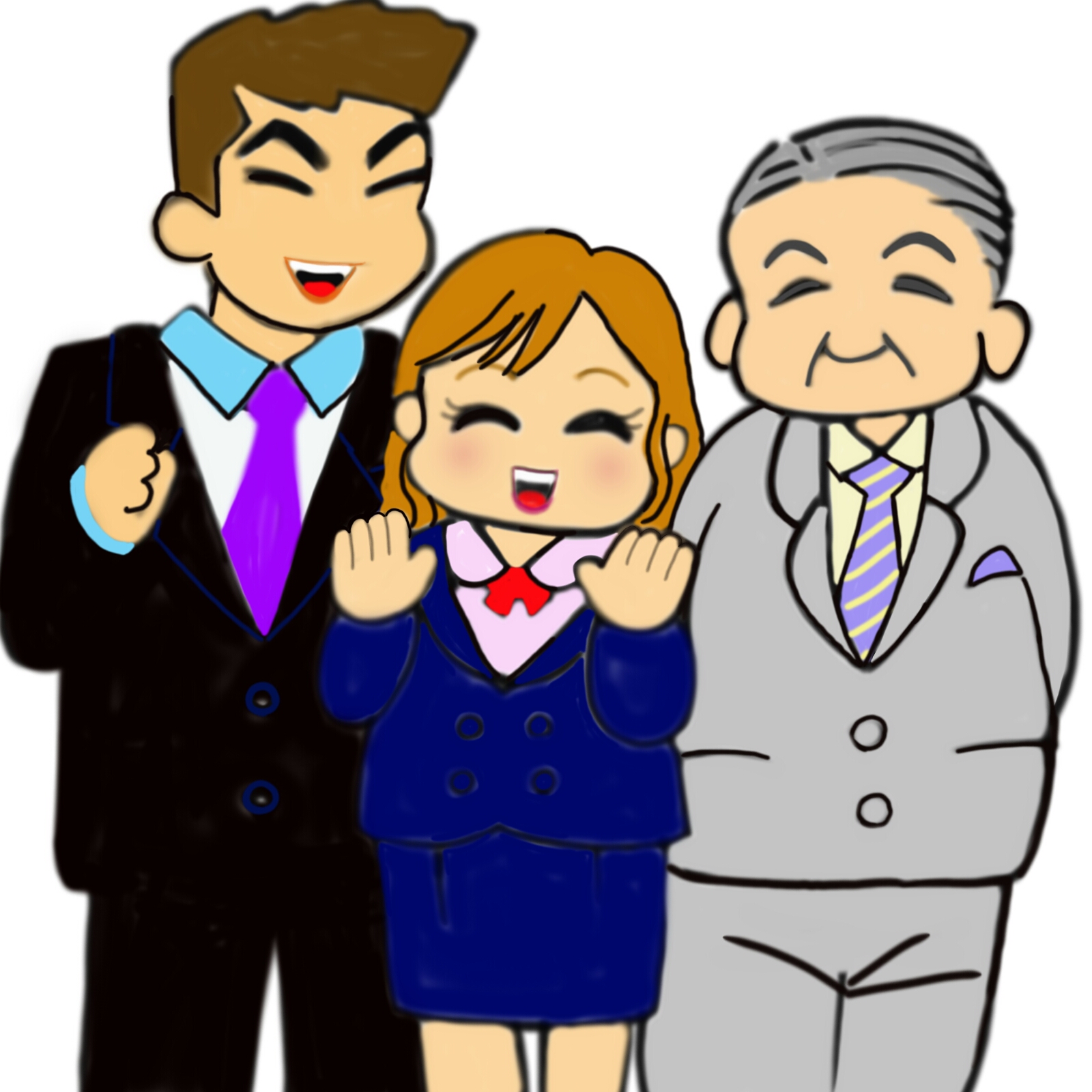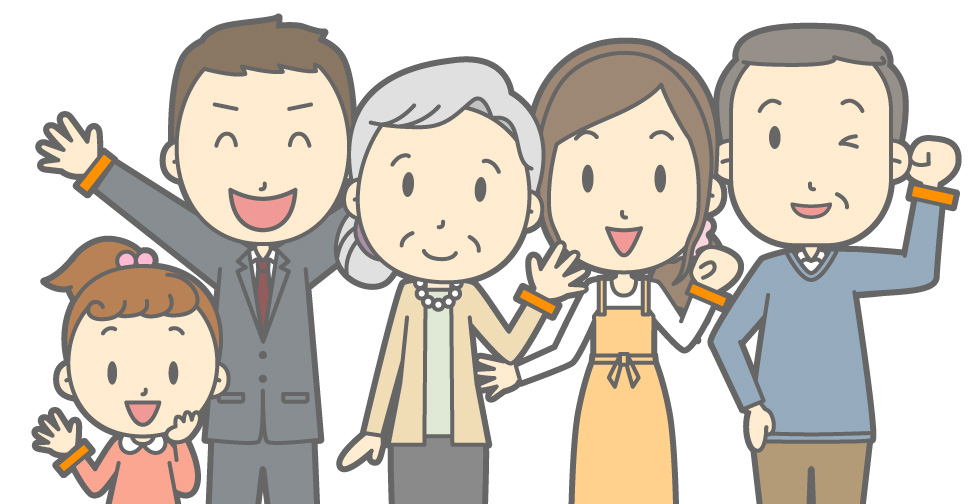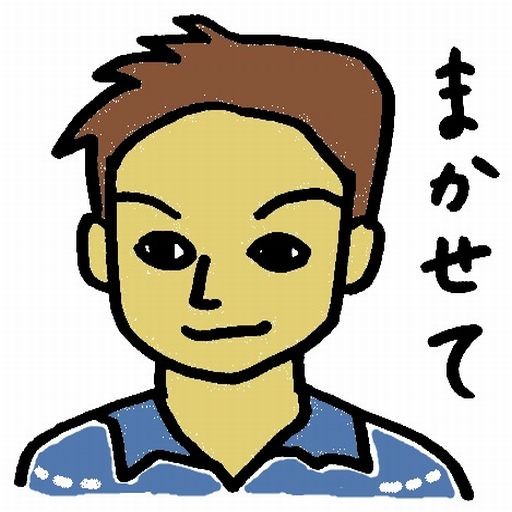「こころの耳」~働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト~
2017/10/09
目次
「こころの耳」~働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト~

こんにちは、青年A(@seinen1234)です。
以前、「「みんなのメンタルヘルス総合サイト」~シンプルで分かりやすい厚生労働省のウェブサイト~」をご紹介しましたが、ここと同じ厚生労働省のサイトです。
めちゃくちゃオススメのサイトです。
「こころの耳」は、”働く人”に特化したサイトです。
大まかなサイト構成をご説明します。
<メニュー>
「相談する」
「知る・調べる」
「学ぶ・実践する」
<切り口>
「働く方へ」
「ご家族の方へ」
「事業者、上司、同僚の方へ」
「支援する方へ」
(僕の感覚ですが、スマートフォンよりもPCの方が見やすいサイト設計となっています)
非常に分かりやすいサイトで、特に、電話、メール相談が充実しているように思います。
うつで苦しんでおられる方は一読されることをオススメします。
詳細は同サイトに任せるとして、僕の記事では、上記4つの切り口で、印象に残った箇所や解説をしたいと思います。
<働く方へ>~1人で悩まず相談しよう。あなたの味方です~
働いていて、うつ病に苦しんでいる方は非常に多いと思います。
僕もその1人でした(詳細は【体験記】を読んでいただけますと幸いです)。
働くうつ病患者は、次の事でお悩みではないでしょうか?
・うつを治す方法
・良い病院の見つけ方
・うつでも仕事をし続ける方法
・会社の辞め方
・辞めた後の生活の仕方
・経済面でのサポート
(自立支援医療制度~医療費負担が1割に~)
・再就職の仕方 など
そのことについて、同サイトの「こころの耳メール相談」や「専門相談機関・相談窓口」、「命を大切にするページ」で気軽に相談することができます。
<働く方へ>では、「コラム「身体のストレス反応から考える職場のメンタルヘルス対策」」が印象的でした。
心身のストレス反応は、不安・憂鬱などの心理的な反応のみならず、肩こり・腰痛、目の疲れ、胃腸の具合などさまざまな身体的な反応としても現れます。
・ストレスと腰痛・ストレスと口の健康など
上記コラムで、ストレスと顎関節症の関係についても語られていました。
持続的なストレスによって、歯の食いしばり、歯ぎしり、上下歯列接触癖(TCH)を発生させ、顎関節症になることがあるということです。
(TCH(歯列接触癖)とは?:顎関節症の最大の原因が発見された!)
僕もストレスからうつ状態になり、顎関節症となりました。
(うつ病と顎関節症はなぜ間違いやすいのか~うつが「原因」で顎関節症は「結果」~)
当時は、うつ病とは気づかず、症状として表れている顎関節症の治療ばかりしてしまい、治るどころか悪化させてしまっていました。
<ご家族の方へ>~苦しい”うつ”を理解してあげてください~
身内がうつ病になると、ご家族はどのように接すればいいか分からなくなることがあります。
(うつ病からの回復は「家族」にかかってる│「うつ」と家族の接し方)
同サイトでは、「接し方のアドバイス」、「病院の探し方」、「相談場所」が紹介されています。
特に印象的だった箇所をお伝えします。
《まずは安心できる場を》
お身体の病気の時と同様に、こころの不調な時も一番大事な基本は「安心して休息する」ということです。
言葉だけでなくさりげない気遣いなどが、苦しむご本人にとっては安心感を与え、ご家庭でゆっくり憩いの時間をとることができます。
病気への発展を防止するだけでなく、回復力を促すこともつながります。
《病気の理解と基本的な対応》
「治療にはご家族の協力が重要」などといわれますと、大きな責務を感じて、ついつい力が入りがちですが、あまり特別なことを考える必要はありません。
まずは力を抜き、病気の理解からはじめてみましょう。分かりにくい言葉は「用語解説」のページをご覧ください。
《原因探しをしない》
「なぜ、この人は病気になってしまったのだろう」「自分たちに何か問題があったのか」など、原因が何なのか家族として大変気になるかと思います。
実際は様々なことが関与して特定できないことがよくあります。
「今できること」を中心に考えるようにしてみましょう。
家族の生活の中で、本人がストレスを感じることがあれば、今は取り除いておくということも大切です。
《無理に特別なことはしないでおく》
ご本人の元気がないと、「気分転換をさせよう、旅行でも連れ出そう、パーッと飲み明かそう」など家族で考えることもあるかもしれません。
しかし、こころのエネルギーが消耗している状態ですと、普段楽しめることは楽しめず、むしろ疲労感を増し、悪化してしまうこともあります。
また、こうした気遣いに応えられない自分に嫌悪感を募らせ、自殺のリスクも高まる場合もあります。
ご本人が、楽しみたくなる気持ちが湧いてくるのを待ちましょう。
うつ病治療は長期戦となることが多い病気です。
ご家族は「待つ」ということが非常に大切になります。
(家族はうつ病患者にどのように接すればいいか?:4つの対応とうつ患者の気持ち)
「体調はどう?」「働けそう?」などと声をかけてしまいそうですが、それは本人が決めることです。
外から見ると、ずいぶん良くなってきていると感じても、本人の感覚としては全く万全ではないことが往々にしてあります。
患者を焦らせてはいけません。
じっと回復を「待つ」ことが大切だと思います。
<事業者、上司、同僚の方へ>~活気ある職場づくりへ~
うつ病を中心とした精神疾患についての理解を深めること、メンタルヘルス対策や過重労働対策の必要性や対策の仕方、相談機関を紹介しています。
「他社はどのようなメンタルヘルス対策をしているのか?」で、事業場の取り組み事例も知ることができます。
<支援する方へ>~多方面からのサポート~
ここでは、<支援する方へ>とざっくりしたテーマで、解説がされています。
「こころの病・克服体験記」や「職場復帰に関わったみんなの声」もあり、サポートするすべての人に当てはまる良記事もあります。
おわりに~まずは、読んでほしい~
うつ病はありふれた病気です。
日本だけで100万人以上の患者がいるといわれています。
そしてネットや書籍で多くのうつ情報が発信されています。
そうした状況で「何が正しい情報で、何が正しくない情報なのか」判断するのが難しくなっています。
中には、自社商品を売りたいがために、ウソの情報を流したり、間違ったことを書いているサイトもあります。
(情報のウソ、ホント。見極める力~意見と事実の違い~)
患者やご家族がそういった情報に惑わされないようにするには、信頼のおけるサイトからの情報を大切にすることが必要かと思います。
そのサイトの1つが「こころの耳」だと思います。
厚生労働省が運営していて、親身になって記事を更新しているのが伝わってきます。
うつ病で悩んでいる方は一読をオススメします。
本日もありがとうございました。
<こんな記事も読まれています>
『ツレと貂々、うつの先生に会いに行く』(細川貂々):「ツレうつ」シリーズ”細川貂々”さんと人気精神科医”大野裕”先生のコラボ本